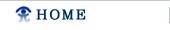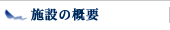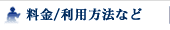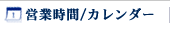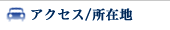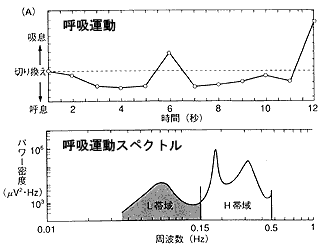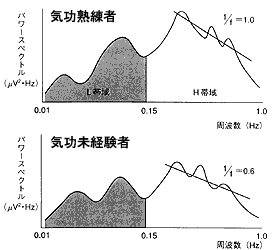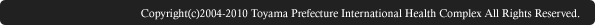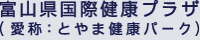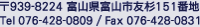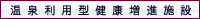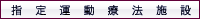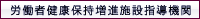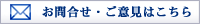研究室だより
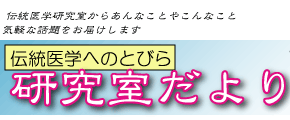 |
 |
| 2003 年 03 月 06 日 号 『気功のゆらぎ効果と癒し』 伝統医学中の“健康運動”の一つとして気功を取り上げて実験した。そのデータの一部を紹介する。 |
|
| バックナンバーはこちら | |
| 1.運動パターン |
| 気功は、普通の身体運動のように有酸素運動(エアロビックス)として把握すると誤解を生じる。気功は健康づくり用の体操であるが、エアロビックスとは異なった運動パターンを示している。気功を神経生理学的に実験してみると、呼吸運動、特に呼息運動が強調された別の運動形態を示す。気功中に呼息の持続時間と量が調節されると、自律神経系活動のバランスが整えられるので、気功は癒し(Healing)につながった体操といえる。 気功は、元々、古代中国の医療(治療)体操として開発され、数多くの流派とやり方をあみ出してきた。現代、中心となっているのが、導引功や益気功中心の内気功であって、自らが気功を実行して“気”を求める方法である。決して第三者の気功師から気をもらうような外気功ではない。その効果は、自分自身が運動して、精神的な健康・癒しを求めていく。 |
| 2.気功の効果 |
||
気功中の呼吸リズムを測定し、さらに周波数分析すると、図1のようなスペクトル波形が描かれる。それをさらに低い周波数帯域(0.05〜0.15Hz)と高い周波数帯域(0.15〜0.5Hz)に区分する。その結果、高い帯域が多く現れるのが、気功熟練者、すなわち呼吸運動をマスターした人である(図2参照)。多く現れた高周波数帯域は、呼吸リズム間隔変動が大きいことを示し、自律神経系の中の副交感神経系活動の促進を示す。これが気功の効果であって、決して筋力増強や酸素摂取量の増大による鍛練法ではない。
気功は激しい動きではなく、息を充分に、思い切って吐くことに努め、10秒以上も吐き続けている。その結果、図2の上のように、スペクトル波形内の回帰直線の勾配(1/fβ)の傾きがβ:1.0に近づいている。この1/f1.0(f-1.0)の値が、“ゆらぎ”と呼ばれ、気持ちが落ち着き、安定した精神状態になったことを示す。神経生理学的に言えば、図中のH帯域が増加し、副交感神経系活動が促進されて、その支配下の内臓諸器官の働きが活発になったことを意味する。 気功は単なる肥満予防用の体操ではなく、呼息運動を強調した、自律神経系活動バランスを整える調節運動である。これを毎日、実施することが、心の癒しに通じ、精神的健康づくりに役立つことになるだろう。 |
| 3.気功と腹式呼吸 |
| 自律神経系のうち、副交感神経系活動が促進され、交感神経系活動が抑えられた場合、“コンディション(体調)”が良いと言われる。図中のH帯域の増加と1/fβの傾き(β)が1.00に近づくことを意味している。この現象が表れ易いのは、気功のような呼吸運動で、特に腹式呼吸が強調された場合である。 腹式呼吸法は気功の中に多く取り入れられ、横隔膜をより上方に持ち上げ続ける方法である。横隔膜(筋肉)が上方に拡大伸展(ストレッチ)すると、筋紡錘から脳に向かって信号が発射され、脳幹の視床下部から癒しの信号が発射され、β・エンドロフィンなどのモルヒネ様のホルモンが分泌されると言われる。その結果、よい気持ちになり、鎮静化された精神状態となってくる。 こうしたヒトの健康づくりや癒しは、腹式呼吸の実行によって効果を高め、体調を整えることができる。今後、「癒しの生理学」「ストレスの解消法」「感性の科学」などが定量化されようとしている。 |
| (永田 晟) |