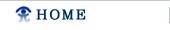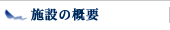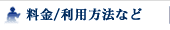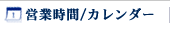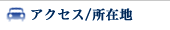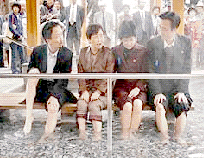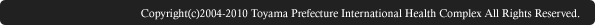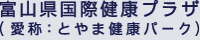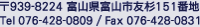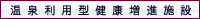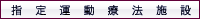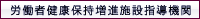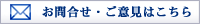研究室だより
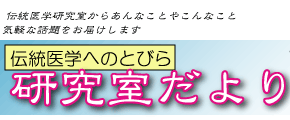 |
 |
| 22003 年 01 月 31 日 号 『足浴に関して』 |
|
| バックナンバーはこちら | |
| "お風呂"といったら |
| 恐らく日本人ほどお風呂が好きな国民はないだろう。日本は島国で資源が乏しいと言われているが、水やお湯(温泉)の資源は他国が比べ物にならないくらい極めて豊富である。そして、ここで生活を営んでいる人々は自然の恵みをフルに活用して、疲労回復や健康増進に役立てている。日本が世界一長寿国として名を知られていることもこのような生活環境と日本人の"お風呂好き"なしでは語れないはずである。 周知の如く、一言でお風呂といっても実に色々な種類があり、その効果、安全性及び入り方などもさまざまである。今回の研究室だよりは、主に今まで研究室で行ってきた実験をもとに、足浴の有効性、安全性、注意事項及び全身浴との違いなどについて紹介したいと思う。 一般的に、入浴法は全身浴、部分浴と特殊な入浴と大別されているが、足浴は部分浴に属されている。古くから中国やヨーロッパでは、自然環境や生活習慣の違いにより、全身浴よりもむしろ部分浴やシャワーの方が日常的であったと考えられる。特に足浴は、商人、軍隊などが長旅の後に疲労解消、老廃物の排除やリラックスゼーションをはかるのに最も簡単、便利で、リーズナブルな方法の1つであったと思われる。このように足浴は単に便宜性、経済性があるだけではなく、医学や生理学的にも、すでにその重要性、有効性が実証され、客観的に足浴の人体における影響を捉えることができた。 中国の伝統医学によると、足には全身経絡(12経絡)の半数を占める脾経、胃経、肝経、胆経、腎経と膀胱経が走っており、ヒトの先天と後天の活力源となる腎、脾胃の機能や精神活動に重要な肝、胆機能と密接に関連するものとされている。更にこれらの経絡上に分布しているツボ(経穴)に温熱刺激を直接与えることによって新陳代謝を促進させるものと考えられる。一方、西洋医学の視点から見ても、膝以下の下腿部は、全身皮膚の9%(両側で 18%)を占め、 筋肉も豊富であるため、温熱刺激の全身的効果が期待できる。また、足はを清潔にすることは心身ともに良い影響を与えることは言うまでもない。それでは、実際足浴を行うことで、からだがどのような生理的変化を示しているのかを実験データを交えて紹介したいと思う。 我々は先ず足浴の実験を2段階に分けて行った。第1段階は単回実験で、主に急性効果を、第2段階は反復実験で、主に慢性効果を観察することにした。 一.単回実験 被 検 者:健常成人男性12名、年齢38±9才 測定項目:循環動態、呼吸器系、脳波、心電図、血中カテコラミン、コルチゾール濃度 入浴条件:水温40℃、入浴時間は15分。各人は対照実験、淡水浴と薬浴を計3回ランダムに行った。 測定条件:入浴15分前から、入浴中(15分)、入浴終了15分後まで、計45分間。 結 果: (1)循環器系 心拍数、心拍出量と心負荷係数はいずれも対照群に比べ足浴群(淡水浴と薬浴)の方が有意に増加していた。つまり、足浴によって循環機能が活発になり、心臓の負担も増加していたことがみられ、全身浴と同様な変化が示された。 (2)呼吸器系 淡水浴群では入浴と同時に呼吸数が増加し、入浴中終始有意な高値を示した。一方、薬浴群では有意な増加が見られなかったが、これは薬浴成分による可能性が考えられた。また、対照群では、変化が見られなかった。 他に、入浴中呼吸商の有意な減少も見られた(薬浴群のみ)が、呼吸商の変化は脂質代謝と関連するものとされ、薬浴中の薬用成分による可能性が考えられた。淡水浴群と対照群では、呼吸商の変化が見られなかった。 また、胸式呼吸と腹式呼吸も同時に記録した結果、足浴により胸式呼吸が次第に浅くなり、腹式呼吸が深くなる傾向も見られた。 (3)神経機能 脳波の変化では、足浴によりα波の増加が見られた。足浴中α1が増加し、足浴後α1、α2とも増加した。つまり、足浴の中枢神経系へのリラックス効果は足浴終了後も持続していたことが示唆された。 (4)血液検査 血中カテコラミン濃度は、足浴群(淡水浴群と薬浴群)では有意に増加し、対照群では明らかな変化が見られなかった。血中アドレナリン濃度は薬浴のみにおいて、浴後の有意な増加を示した。つまり、淡水浴群より薬浴群の方が交感神経機能への影響が大きいことが考えられた。 以上の結果から、足浴は全身浴と同様な循環器系への促進作用が明らかになった。更に、呼吸機能や神経機能にも影響を与え、同様にリラックス効果が得られることも示された。また、単なる淡水浴よりも薬用植物や深層水などを配合した薬浴群の方が、より顕著な入浴効果が得られることも観察できた。 二.反復実験 被 検 者:健常成人男性12名、年齢42±10才 検査項目:免疫機能(リンパ球のサブポピュレーション)、OSA睡眠調査表。 入浴条件:水温40℃、入浴時間15分、3日間連続で1日2回(朝と夜)、薬浴を用いて、クロスオーバー法により薬浴入浴群と対照群で行った。 測定条件:連続入浴するの前と連続入浴した後の計2回 結 果: (1)免疫機能 対照群ではCD4とCD8がほとんど変化しなかったのに対し、薬浴入浴群では両者とも増加が見られ、特にCD8(サプレッサーT細胞)の増加が顕著で、免疫機能の変化が見られた。 (2)睡眠の質 OSA睡眠調査表を解析した結果、寝付いてうとうとした時間が足浴により減少し、寝つきが良くなったことが示された。また、起床時に感じた昨日の疲れの残存感は、足浴により少なくなったことから睡眠の質を向上させることが示唆された。 以上の結果から、足浴は全身浴と同様に循環、呼吸、神経、免疫機能を促進、向上させることが明らかになった。また、全身浴に伴う過度な血圧の変化や発汗によって起きる血圧の急激な変化、血液の粘度増加などの危険要素を最低限、抑えることができると思う。 更に文献調査によると、睡眠前の足浴は睡眠の質を高め(stage3の増加、REM睡眠の減少)、全身浴より優れているとの指摘もあり、また、足を温めることで呼吸器系感染がかかり難い(肺泡の表面の免疫細胞機能が活性化される)との報告もあり、何れも我々の実験結果を支持するものであった。 以上の実験結果を踏まえて、今度は足浴の安全性、温度依存性と入浴時間について検討を行った。足浴の温度は38℃、40℃、42℃に設定し、足浴実施前(10分)、実施中(30分)と足浴後(10分)における循環、呼吸、自律神経及び神経系(脳波と脳血流)の変化を観察することにした。循環器系への影響は前述のとおり、心臓に与える負荷は入浴温度が高ければ高いほど早期に増加し、38℃では明らかな変化がなく(増加傾向があるのみ)、40℃では約25分、42℃では約15分に最大負荷となっていた。また、入浴温度42℃では、20分以上過ぎると脳内圧の上昇と関連する指標が著しく増加することが観察された。更に、頭部の組織血液流量を示す指標では、入浴開始25分の時点でピークに達したことが示された。この他、足浴の快適さをフェイススケール・スコアを用いて評価した結果、対照群(何もせず、50分間座位を保つだけ)の最も低い快適さ(不快感)に達する時間が一番早く(10分)、次に42℃、40℃、38℃の順に10分から25分の間に分布していた。 総合してみると、 (1)足浴による生体の変化は入浴温度に依存して活発になることが明らかになった。過度に負荷をかけることが望ましくない方は、低めの入浴温度を選ぶべきであろう。 (2)入浴時間は入浴温度に伴って随時変更すべきである。つまり、38℃は20-25分、40℃は15-20分、42℃は10-15分が目安であろう。 |
| 最後に少し実用的な話しをしてみましょう! | |||||
| 足浴は単に保温作用、疲労回復、身体清潔、リラックスだけが利点ではない。使い方によっては、今まであなたが抱えていた悩みが解消できるかもしれない!冷え性や生理痛のある方でも、足が熱くてイライラしている方でも、足浴をすることで末梢のみならず、全身が温めるられる。また、イライラした気持ちもお湯に足を漬けるだけで落着いてくるはず。足浴にはこのような二相性効果があるとされている。 足浴の方法、 (1)温度はやや高めにすること(42℃が最適かな) (2)お湯の量はくるぶし以上になること(膝下10cmまでが良い) (3)足浴の時間は10-15分で、冬は長めに、夏は短めに(15分程度) (4)足浴終了後、水を拭取り、手で足を揉んでみよう。 または足の裏を温かくなるまで擦りましょう。 (5)足浴終了後水分を少々補充しよう。 こんな時は足浴をやめましょう! (1)食後2時間以内 (2)風邪などで高熱がある時 足浴の楽しみ方、 (1)体調、目的に合わせてアロマオイルを併用する(ラベンダー、 ローズマリ、ペーパーミントなど)。 (2)好みの入浴剤を使う(お風呂の入浴剤でもOK)。 (3)専門医に体質に合う薬浴処方をしてもらう(健康増進、疾病治療)。 (4)特殊な足浴を試みる、例えば、ゼリー浴、砂浴、セラミック浴(遠赤外線 とマイナスイオンを放出)など。
足浴は極めて簡単、便利な養生法といえるが、長期的に持続することでその効果は倍増するものと考えられる。最近市販されている足浴器の中では、発泡スチロール製が特に安価、軽量、断熱効果抜群などの長所があり、推薦したい一品である。また、写真のように、各地に公共の露天足浴場が設置されるようになり、足浴が益々人々に親しまれることに違いない。足浴の醍醐味を知れば、足浴が止められないかもしれない! 中国では、"知足者常楽"ということわざがあるが、"足りるを知るは常に楽なリ"という意味で、ここでは"足浴を知る(する)者は常に楽なリ"と言いたい。 春天洗足、開陽固脱; 夏天洗足、暑湿可怯。
|
| (許 鳳浩) |